セミナー司会のまとめコメント|台本に書かれていないときどうする?
- 2021.10.21
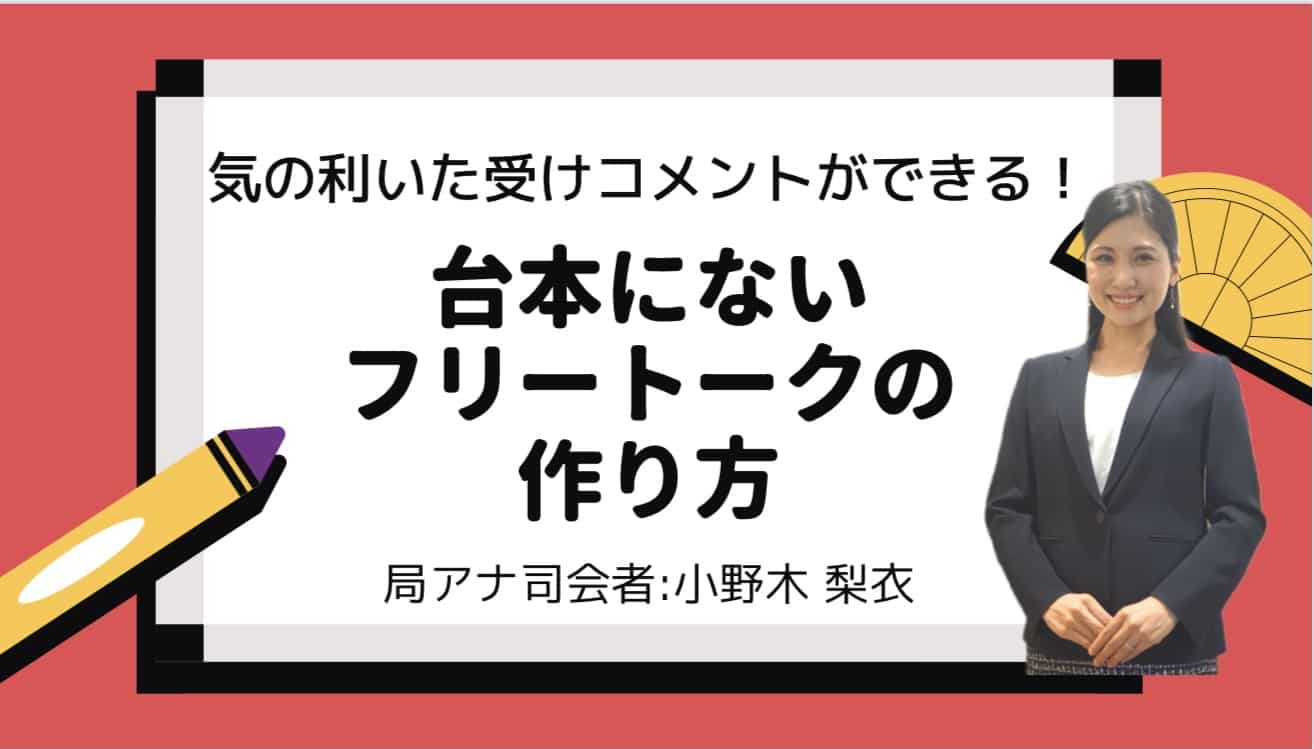
こんばんは!
フリーアナウンサーの小野木梨衣です。
2021年10月19日、名刺アプリEight(エイト)でお馴染みのSansan様にてビジネスマッチングイベント「Meets ONLINE LIVE」の司会を務めさせていただきました。
司会者である私の仕事は、大きく3つ!
- 明るく期待感の高まる雰囲気作り
- 登壇者の人柄や熱量が伝わるようなフリートーク作り
- サービスが印象に残る受けコメント
です。
今回は、登壇者の発表を受けてコメント(受けコメ)を入れる際に、意識していることや、台本に書かれていなくても良い受けコメントができる秘訣についてご紹介します。
実は、受けコメントには3つの型があるんですよ!
早速行ってみましょう!
フリートーク作りについてはこちらの記事にも記載しています。
1、受けコメントには3つの型がある
そもそも受けコメントとは、登壇者の講演やスピーチ後に司会者がするお礼と感想を述べる部分のことです。
台本には、「〇〇様、ありがとうございました。(感想一言)」と書かれていることが多いです。
「〇〇様、ありがとうございました。」
のあとに、気の利いた感想を短く、場が閉まるように述べるのです。
この、(感想一言)って……なんやねん!!!!むずいねん!!って思いません?笑
私もこの(感想一言)記述に怯えていた時代がありました😂
レギュラー司会で入っているMeetsでは、1社あたり6分間のサービス説明プレゼンを聞いたのち、司会者の受けコメントがあって、次の登壇者への振りへと続いていくんですが、
この受けコメント部分は、私がその場でプレゼンを初めて聞いた感想を話しているんですよ♪
受けコメをするときに意識しているのは、
- 見ている方の共感が得られること
- そのサービスの他にない強みを強調してあげること
つまり、聞いている方にとって何が刺さることなのかわかっていることが大切なんですね。
視聴者は何に困っていて、(←課題)
何を解決できたらいいと思っているのか。(←解決方法)
どんなものを求めて、このオンラインセミナーに参加してくださったのか。
そこがわかっていないと、いい受けコメントは生まれません。
ここで具体例を出してみましょう。
3流の受けコメント
「サービスの魅力がよく伝わってまいりました。」
2流の受けコメント
「話しかけるように語ってくださったので、サービスの魅力がよく伝わってまいりました。」
1流の受けコメント
「〇〇だけでなく、〜までできちゃうなんて非常に頼もしいサービスだと感じましたが、みなさんいかがでしたか?
今回ご覧いただいている方への特別オファーとして初期利用料が無料になるということですよ!」
いかがでしょう?
3流と2流、さらには2流と1流の違い、わかりますか?
さらには、この受けコメント、汎用性があることにお気づきになりましたか?
話の内容は違っても、〇〇や〜〜の部分に言葉を入れて話せば受けコメになっています。
これがまさに
受けコメントに検定などありませんが笑、プロ司会者の目線から見ると、このようにレベル分けができると思います。
- 3流司会者:「ありがとうございました。」以外にも、実感のこもった受けコメントができる
- 2流司会者:サービスを要約できなくとも、登壇者のキャラクターに言及した受けコメントができる
- 1流司会者:サービスの要点を的確に捉えたコメント、視聴者への呼びかけ、視聴者にとってのメリットを復唱する受けコメントができる
本番は登壇者のプレゼン中に、スタッフからこの後のセクションに関する指示、訂正や追加コメントが入ったりしますし、出演スタンバイもしなければなりません。
最初から最後まで集中してじっと聞く事ができないことも往々にしてあります。
だからこそ、事前に登壇者のサービスについてネット検索して公式サイトやPRTIMESを見たり、
リハーサル時に登壇者に他にはない強みや今回強調して伝えたいことについて聞いたりといった準備が役に立ちます。
2、万全な準備ができない時、受けコメントどうする?
でももっと正直な話をすると・・・・
台本に目を通すのが精一杯で、事前リサーチはできずに本番日を迎えてしまうこともあります。(小声)
皆さんもきっとそうじゃないですか?
「時間があれば万全に準備してもっと上手くできるはずなのに・・・」
うんうん、みんなそうです。
「本番中にもう少し集中して聞けたらいいコメントできたのに・・・」
いえいえ、スタッフとの打ち合わせもあなた(司会者)の大事な仕事ですよ。
じゃあどうするか。
そんな時に心強いのは、受けコメントの型を持つことです。
ぜひ、1流、2流、3流の型を思い出してください!
話の内容までしっかり聞けなかった時は、3流受けコメントでも良しとする。
話の内容を聞けた時は、サービスの強みや視聴者にとってのメリットといった要点を抑えた1流コメントを目指す!
これができれば、ミスなく、メリハリのある司会進行になります。
新人の頃は、”型”を持ち合わせていなかったので、
うまくできる日とできない日の波が激しいタイプでした(苦笑)
でも、この”型”があることに気づいた時から、すごく気が楽になり、
台本に書かれていなくともフリーコメントがするする出てくるようになりました。
人間ですから
「今日は冴えてるなぁ〜!無敵かも〜♪」と自惚れする日もあれば(笑)、
「事前準備不足でちょっと不安だから緊張してるな、慎重に行こう。」という日もあります。
どんな時もつつがなく、スムーズにイベントを納めるのが司会者の大事な仕事なのですから、
何も全て特大ホームランな受けコメントでなくてもいい、と割り切って臨んでいます。
こうしたある種の割り切りが、安定感を保ちつつ、アグレッシブさのある司会進行に繋がっていると自負しています。
3、あわせて読みたい司会コラム

今回は司会者が台本になくてもいい受けコメントができる秘訣についてご紹介してきましたがいかがでしたか?
Sansanさんのライブ配信イベントは、約1時間の放送のために、前日から配信チェック、リハーサルが行われ、
本番日でも司会リハーサルや登壇者との掛け合い部分リハーサルが行われているんですよ!
たくさんのプロスタッフのスキルによって、事故のない安定した配信映像をお届けできていることに感謝です。
ここまでお読みいただき、ありがとうございました!